研削砥石 特別教育:研削砥石の資格(といし特別教育)の実施案内
『機械研削』・『自由研削』における 「研削といしの取替え等の業務に係る」特別教育講習会実施のご案内
弊社では「E-ラーニング」により学科・実技の「特別教育」の全てを実施します
●弊社の「安全衛生法第59条3項のといし取扱等の特別教育」の大きな3つの特徴!!
①.『e・ラ-ニング(デジタル動画コンテンツ)』にて法令上の必要資格を完全取得できます。
②.「機械(平面研削盤等)」と「自由(サンダー等)」の 2種類の必要資格を1回で取得できます。
③.「安全衛生法」上の適正な『修了証』の発行を行います。
(『機械研削講習』と併せて『自由研削講習』の同時受講となり、下記料金にて、2日間で両方の資格取得が出来ます。)
| 実施日 | 実施場所 | 募集状況 | ||
| 2025年09月実施 | 25日(木)・26日(金) | 貴社にて | 受 付 終 了 | |
| 2025年11月実施 | 27日(木)・28日(金) | 貴社にて | 受 付 中 | |
| ¥19,000-(1名)(テキスト代含む)消費税別 ※ご受講料について:今後テキストの価格改定により変更となる場合があります。 「成形平面研削(側面・溝加工における)」と「円筒研削」のどちらかの作業をされる可能性がある場合には「通達」による「特別講習」も含めて¥23,000(テキスト代含む)消費税別となります。 ⇒ 「通達」とは、安全衛生規則120条に係る技能と条件を満たす講習を指します。 |
||||
2025年9月05日(金)更新
●※1.受講カリキュラムの日程は2日間です。(1日目 9:00~17:00 / 2日目 9:00~15:00)
* 実施場所について:実施場所は弊社会場でなはく、弊社提供の「動画コンテンツ」を含む教材を貸出し、貴社にて実施して頂く方法となります (現時点で実施場所を弊社会場で行う予定はございません)
●※2. お申込み時の注意事項(ご受講料について)
実施日1ヶ月を切ってから、または該当月の受付終了後はキャンセル不可とし、貴社ご都合により実質ご受講されない場合であっても理由の如何を問わずご受講料は 100%ご負担頂くものといたします。
●※3.上記「定期開催」とは別に「別料金」で「特別日程による開催」を希望される方は
⇒090-8753-3960:担当「植田」迄
~安全衛生特別教育規程に従い、以下の内容で e-ラーニング(デジタル動画コンテンツ)により実施します~
<機械研削及び自由研削>
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| 機械研削用研削盤及び同といし、 自由研削用研削盤及び同といし、 取付け具等に関する知識 |
機械研削用研削盤・自由研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 機械研削用といし・自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 覆い 保護具 研削液 |
4時間 |
| 機械研削用といし及び自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 機械研削用研削盤と機械研削用といしとの適合確認、自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認 機械研削用といし及び自由研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法 | 2時間 |
| 関係法令 | 法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
| 実技教育 | 機械研削用といし・自由研削用といしの取り付け方法及び試運転の方法 | 5時間 |
※上記内容を中央労働災害防止協会発行の「グラインダ安全必携」に従い実施します。
●対象労働者の「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」の受講が労働安全衛生法で義務付けられております。
●労働安全衛生法第119条により、規定に違反した者は六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。
●「特別教育」を受けずに“といしの取替え”を行なうと、会社や事業主は罰せられます。
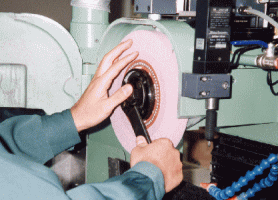
《お問い合わせ先》
株式会社 ウエダテクニカルエントリー
〒614-8174 京都府八幡市上津屋八王子75-1
(E-mail)aag26500#pop02.odn.ne.jp
(FAX)075-982-6655
(#を@に変更してご使用下さい)
※ 本特別教育講習の2日目:実技講習終了後に【といし特別講習:成形研削加工<側面・溝加工>】を同時開催しております。(特別教育講習とあわせてご受講ご希望の方はお申し付け下さい。詳細はこちら)
●「E-ラーニング」による「特別教育」実証の「メリット」について
⑴「移動リスクのメリット」
・今までの一般的な講習では自社から講習会場までに社員を行かせる為に「交通費」や「本人の移動リスク」を会社が負担していたがこの「移動のリスク」が無くなる
⑵「自社環境での実施のメリット」
・他社での講習に比べて「E-ラーニング」の動画コンテンツは「停止」や「見直し」をして受講者のペースで学べる
・「E-ラーニング」の動画コンテンツを見ながら同時に自社の設備を使用して学べる
※「コロナ感染症」の様なパンデミックリスクへの大きな対策になります
●外国人労働者への「特別教育」について
・近年「技能実習制度」の「特定技能」への移行に伴い「厚生労働省」は母国語での講習を義務付けようとしており、弊社関連会社(株式会社日本製造京都工芸社)にて対応しております。
「対応言語:インドネシア語/中国語/タイ語/ベトナム語/他」






